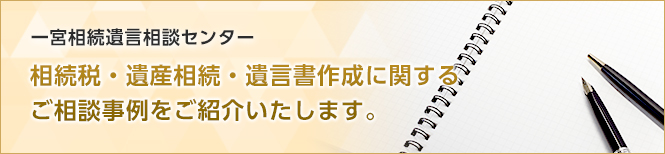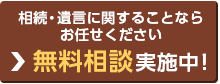2026年02月02日
Q:税理士の先生に相談です。相続税申告を専門家に頼まずに行うというのは可能でしょうか。(一宮)
私は一宮在住の50代会社員です。先月私の母が亡くなって現在相続の手続きが発生しております。母の相続財産は実家や預貯金が主であり、相続人は父と私の2人です。母の総資産額を考えた場合、相続税申告が必要とされる金額に届きそうな予感がするので、税務署から通知が届くより前に自ら手続きしておかないといけない…という事までは認識できています。相続手続きを行うにあたって、相続税申告を行った友人知人の数人に話を聞きました。それによると、税理士などの専門家に頼んだという友人もいましたし、自分で全て手続きしたという友人もいました。自分で全て手続きを終えられるのであれがプロの手を借りずに相続税申告を行いたいというのが正直な気持ちですが、難しいポイントや税理士の先生などに依頼した方がメリットが大きい事柄があれば伺いたく、一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせをさせて頂きました。その上で相続税申告のお手伝いを依頼するかどうかを考えさせてもらおうと思いますので、よろしくお願いします。(一宮)
A:税理士に依頼したほうが安心で確実ですが、ご自身でも相続税申告行う事は可能です。
この度は一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせ頂きありがとうございます。
ご相談者さまがおっしゃる通り、税理士にご依頼をせずにご自分で相続税申告を行う方もいらっしゃいます。しかし、相続税申告を税理士などへの専門家へ依頼するという事は、その手続きを確実性を高めるため安心といえるでしょう。常識で考えても煩雑な相続税申告が手馴れている方は、まず少ないでしょう。その内容への理解が不十分・不明瞭なまま申告を行って、本来の納めるべき税金よりも多く納税する、もしくは過少申告によって過少申告加算税を税務署から求められる事もあります。そして、相続税申告に設けられている明確な期限に間に合わなければ、延滞税などのペナルティが加算される事も忘れてはなりません。相続税申告を行う以前には相続人の遺産分割が決定している事が基本となりますので、遺産分割協議でその内容が決定次第すみやかに相続税申告手続きへ進む事が理想といえます。その間の10か月というのは決して長い期間とは言えず、その手続きにはスピード感が求められます。
一宮のご相談者様は相続財産にご実家が含まれますので、土地・建物の評価計算や名義変更などの登記も必要となります。その点を考慮しても内容が煩雑になることが見込まれます。
経験や知識と言ったものが無い状態からスタートして手続きを行う事は不可能ではないものの、それに過剰な負担を感じた多くの方、もしくは確実な手続きを安心して行いたい方などは、早めから税理士などプロへの相続税申告業務代行の依頼を行っている訳です。
一宮相続遺言相談センターでは、一宮の地域の皆様から頂いた相続税申告代行依頼を承っております。相続税に関するご不明点やご不安が少しでもある方は、ぜひ一宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。地域の皆様の相続税申告のお手伝いを全力でサポートいたします。一宮の皆様のご来所を所員一同お待ち申し上げております。
2026年02月02日
Q:死亡保険金を受け取った場合の相続税申告はどうなるのか税理士の先生に伺います。(一宮)
昨年一宮の父が亡くなって、葬儀や亡くなってすぐにやらなければならない手続きなどは終わらせました。これから相続手続きをするため、色々調べ始めているところです。相続人は母と私の2人です。父の遺産は現金が1000万円程度と自宅になるかと思います。我が家はごく普通の一般家庭ですので、とくに相続税申告は必要ないだろうとのんびりしていたのですが、最近、母が死亡保険金を受け取っていたことが分かり、相続税申告が必要になるのではないかと少し動揺しています。死亡保険金が相続税申告でどう扱われるのかがわからないため、それによって相続税申告が必要になるかもしれません。母が受け取ったのは1500万円程度ですが、死亡保険金が相続税申告の課税対象になるかどうか税理士の方に伺います。(一宮)
A:相続税申告の課税対象になるかどうかは、まず契約書を確認します。
まず、死亡保険金は民法と税法でその扱いが異なるためご説明します。
民法上では、受取人固有の財産として見なされるため、相続財産には含みません。しかしながら、税法上では「みなし相続財産」として扱われ、遺産分割協議の対象外ですが、相続税の課税対象です。
つまり、死亡保険金は相続財産ではないため、相続人で分割する必要はありませんが、相続税申告の対象ということになります。ただし、死亡保険金は誰が契約者で、誰が受取人であるかによってかかる税金が異なるため、先に契約書を確認する必要があります。
・【相続税】契約者=被保険者、受取人が相続人
・【所得税、住民税】契約者=受取人、契約者と被保険人が異なる
・【贈与税】契約者と被保険者が異なり、受取人も第三者
被相続人(亡くなった方)が、死亡保険金の保険料の全額ないし、一部を負担していた場合の受け取った保険金は「相続税の課税対象」です。ただし、死亡保険金には非課税限度額が設けられています。下記の計算式をご参照のうえ、相続人1人につき500万円として計算し、算出した額を超えた金額が相続税の課税対象と算ります。なお、相続人以外を受取人とする死亡保険金の非課税限度額は設けられていません。
【死亡保険金の非課税限度額の計算式】 500万円 × 法定相続人の数
ご相談者様に当てはめて計算してみます。
相続人:お母様とご相談者様の2人
受け取った死亡保険金:1500万円
非課税限度額→500万円×2人=1000万円
したがって、受け取った1500万円の死亡保険金のうち1000万円が非課税限度額で、
残りの500万円が相続税申告の課税対象ということになります。
相続人が生命保険金を受け取っていた場合、相続税申告の課税対象かどうかの確認が必要です。相続税申告には期限があるため、早急に相続税申告を専門とする税理士へご相談ください。
相続税申告は正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続税申告を得意とする一宮相続遺言相談センターの税理士にお任せください。一宮をはじめ、多数の地域の皆様から相続税申告に関するご依頼を承っている一宮相続遺言相談センターの専門家が、一宮の皆様の相続税申告がよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、一宮の皆様、ならびに一宮で相続税申告ができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
2026年01月06日
Q:取り急ぎ税理士先生に相談です。家庭の事情により相続税申告の期限を延長したいと考えています。(一宮)
私は50代の主婦です。少し前に一宮に住んでいた私の父が癌により亡くなりました。父は母と姉と同居していた事もあり、地元の一宮での葬式や供養、父の遺品の整理や片付けなどについても母と姉中心でスムーズに行う事が出来ました。遺産についても、自宅と銀行口座にある数百万円のみという事だったので、特に相続税申告は必要ないという事で幕引きできたと思っていました。
しかし、ここにきて父の死亡保険金、しかもそれなりの金額を母と姉が受け取っていた事が分かりました。その生命保険の受取人には私が含まれていなかったので、全く気が付きませんでした。しかし生命保険金はみなし相続財産として一部の非課税枠を除いた金額については相続税申告をしなければならないらしいのです。
私が受取人に含まれていないため母と姉は伝えにくかったのかもしれませんが、相続税申告には期限があるため冗談ではないと思いました。最終的に闘病した父をずっと支えてきた二人を死亡保険金の受取人にするのは理解できるものの、なぜそれを私に伝えてくれないのか言葉にできない憤りを感じました。
死亡保険金を含めると、相続税申告は必ずしなければならない金額だと思います。遺産分割についても、まだ何も決まっていません…このような状況なので、相続税申告を行う締め切りを延ばしてもらう事は可能でしょうか。(一宮)
A:ご相談者様の理由では、相続税申告期限の延長はまず難しいとお考え下さい。
この度は一宮相続遺言相談センターまでお問い合わせ頂きありがとうございます。
ご相談者様が大変お困りのことであろうとお察しいたします。まず相続税申告の期限ですが、これは被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内、その事は勿論ご存じの事と思います。ところが今回のご事情での相続税申告の期限延長は、まず認められないと考えられます。期限延長が認められるケースというのは、遺贈の放棄があった場合や何らかの理由により相続人に異動が生じたりする場合などであり、遺産分割や準備が間に合わないといった個人的な事情での延長は出来ないと考えて、まず間違いないと思います。
なので、期限延長を行う以外の対処方法を考えていきましょう。遺産分割が決まっていなくても、未分割で申告して納税する方法があります。仮に法定相続分で受け取ったとして計算をして、相続税申告および納税を行います。その際は「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の特例」の適用が出来なくても、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくと、改めて申告する際に適用する事が可能ですので、その点は安心して良いかと思います。不足分を納めるための申告が「修正申告」、逆に納めすぎた場合の還付請求は「更正の請求」と言います。
一宮相続遺言相談センターでは、相続税申告に関する一宮の皆様のお困りごとを全力でサポートいたします。一宮の皆様に向け、初回は無料でご相談を承っております。相続税に関するご不明点やご不安があれば、どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にお問い合わせください。一宮の皆様のご来所を所員一同お待ち申し上げております。