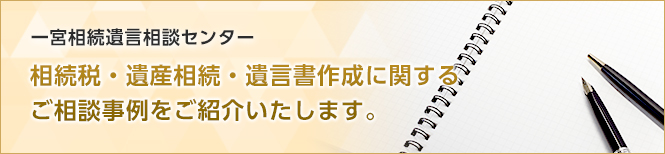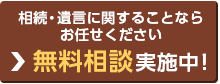2021年06月04日
Q:税理士の先生に相談です。相続税の対象になる実家の評価方法を教えて頂きたいです。(一宮)
現在一宮に住んでいる50代主婦です。先日、一宮市内の病院で父が亡くなりました。相続人は、おそらく母と子である私の2人だと思います。
父の相続財産として一宮にある実家といくらかの預貯金がある程度でした。実家の評価額によっては、相続税申告を行う必要があるということはわかるのですが、評価方法がわかりません。
そこで税理士の先生に相談です。実家の評価方法について教えて頂きたいです。(一宮)
A:建物の評価の場合は固定資産税評価額、土地の場合は路線価で評価したものが評価額となります。
この度は、一宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
相続税申告を行う際には、ご自宅等の不動産の評価が必要になります。しかし不動産の場合、預貯金のようにそのままの金額で評価することができません。そのため法律で規定されている方法で評価していきます。評価をする際、自宅は土地と建物に分けます。
建物の評価を行う場合、固定資産税評価額が評価額となります。毎年5月頃に固定資産税納税通知書届くと思うのですが、そちらで固定資産評価額を確認することができます。固定資産税納税通知書は、各市町村によって様式は違いますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額となります。また、注意する点として固定資産税評価額は課税標準額とは異なります。
続いて、土地の評価を行う場合、国税庁によって規定されている路線価を用いて評価を行います。路線価とは土地の時価を指します。国税庁のホームページにて路線価は掲載されていますので、そこから確認してすることができます。この路線価によって計算された評価額からその土地の形状や面積、周辺の環境などを考慮し評価額を下げることができます。路線価が定められていない地域では倍率方式という方法で計算します。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率をその土地の固定資産税評価額に乗じて計算を行います。路線価、倍率方式どちらも評価を適切に算出するには多くの専門的な知識が必要となります。そのため、相続税申告が必要な場合は税理士等の専門家へご依頼することをお勧めします。
一宮相続相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆さまの相続税申告を数多くお手伝いさせていただきます。一宮近隣にお住まいの皆さま、相続税についてご相談を受け付けております。まずはご自身の財産の状況を無料相談にてお聞かせください。お客様の状況に合わせて、専門的なサポートをさせていただきます。
一宮相続遺言相談センターは、一宮の皆さまからのお問い合わせ心よりお待ちしております。
2021年05月07日
Q:父が亡くなり相続手続きをしないといけないのですが、何も知識がなくわかりません。相続税について税理士の先生に教えていただきたいです。(一宮)
一宮の実家に暮らしていた父が先月亡くなりました。父の財産は実家と預貯金、その他にも所有している土地があります。また、父は会社を経営していたため、その点でも相続税が発生するだろうという事はわかっています。自分でいろいろと調べてみましたが、専門的な言葉も多く、財産の種類も多いためよくわからず困っています。私は就職して一宮から出てしまっているため、なるべく一宮に行く回数を減らしてスムーズに相続手続きを進めていきたいと思っています。財産調査をして、期限までに相続税申告をしなければいけないことは何となく理解しています。なにが相続税の対象となる財産かもわからないため、まずは相続税について詳しく教えていただきたいです。(一宮)
A:相続税には課税される財産と非課税の財産がありますので、下記にて確認していきましょう。
ご相談ありがとうございます。
まずは、被相続人が亡くなられたら進めなくてはいけない手続きの流れについて解説していきます。
- 相続人の調査…相続人の相続関係を客観的に証明するために必要となる
- 相続財産の調査…遺産分割や財産の相続税申告、名義変更などを進めていくうえで、間違いがないように調査を行う
- 遺産分割協議…相続人全員で遺産分割を決める話し合いをする
- 相続税申告…遺産総額が基礎控除の金額を超える場合に申告をする
- 相続財産の名義変更…不動産や預貯金などの名義変更をする
上記の流れに沿って進めていきますが、相続税には課税される財産と非課税の財産がありますのでこちらも併せて確認していきましょう。
【課税対象の相続財産】
- 土地や家屋、土地に関する権利
- 事業用、農業用財産
- 有価証券、株式
- 預貯金
- 家庭用財産
- 乗り物
- みなし相続財産
- 相続や遺贈により財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に受けた贈与
- その他
【非課税の相続財産】
- 墓地・仏壇・仏具など
- 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
- 心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 生命保険金
※相続人が受取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
- 死亡退職金の一部
※②相続人が受取った退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで非課税
- その他
一宮にお住まいの皆さま、相続税申告でお困りのことがあれば、一宮相続遺言相談センターまでぜひお問い合わせください。必要書類の収集や作成、相続税申告まで相談者様の意向に沿いながらサポートが可能です。
一宮の相続税に関するお手続きに経験豊富な専門家が対応いたします。家庭の状況や所有する財産によっても進める手続きは異なりますので、まずは初回の無料相談にお越しいただきお話をお聞かせください。
一宮にお住いの皆さま、一宮に財産がある方からのお問い合わせ、心よりお待ちしております。
2021年03月03日
Q:父が亡くなり、書斎を片付けていたら多額の現金が見つかりました。相続税申告の際の扱いはどうしたら良いか税理士の先生にお伺いします。(一宮)
一宮で相続税に特化した税理士事務所との事でご相談させて頂きます。私は一宮生まれですが、今は他県で暮らしている会社員です。先日、一宮郊外の実家で一人暮らしをしていた父が亡くなりました。一宮に住んでいる妹と一緒に実家に行って遺品整理をしたところ、いわゆる“たんす預金”が見つかりました。金額的には数百万円あるかと思います。相続税の手続きにおいて、このたんす預金の扱いが分かりませんので税理士の先生のアドバイスを頂けたらと思います。もしかしたらまだ他にも現金が見つかるかもしれません。実家も父の遺産になるかと思いますので、たんす預金も相続税申告の対象となるようでしたら、相続税の申告が必要になる可能性があります。(一宮)
A:被相続人が手元に置いていた現金も相続税の課税対象となりますので、まずは税理士に相談されることをお勧めします。
銀行に預金してあるなしに関わらず、被相続人が所有していた財産(現金、不動産、株など)は全て相続税の課税対象です。よってお父様が自宅で保管していた現金も相続税の課税対象となりますので、改めて遺品整理を行って他に相続税の課税対象となる財産が残されていないか確認してみてください。全ての財産の総額を集計し、相続税の申告をする必要があります。相続税の課税対象かどうかの判断は税理士に任せるとご安心かと思います。
相続税の申告は申告納税制度といって、相続人が相続税を計算し申告しなければなりませんが、相続税に特化した税理士に依頼することも可能です。また、申告対象となる資産全てについての内容証明が必要となるわけではありません。自宅などに保管していた現金については、銀行に預けている預貯金のように金額の証明書がないので正確な金額を証明する必要はありませんが、なるべく正確に、相続人が確認できただけの現金を集計して相続財産として申告しましょう。
税務署は生前の所得金額を把握しており、税務調査が入った際には金融機関の口座などを調査され過去の所得水準と比較されます。被相続人の口座だけでなく、相続人の口座にも死亡日前後で多額の入金や不自然な動きがないか確認され、疑わしい場合は事情説明を求められます。相続税の課税対象である財産を申告せずに家で保管することは絶対にやめましょう。
相続税申告は複雑で決まり事も多く、慣れない方には難しい分野ですので相続税専門の税理士へご相談される事をお勧めします。一宮相続遺言相談センターでは経験豊富な税理士が一宮の皆様の相続税申告のサポートを行っております。一宮の地域事情に詳しい税理士が一宮の皆様の相続税に関するご相談をお受けしております。初回のご相談は無料ですので、一宮の皆様、どうぞお気軽にお問合せください。一宮の皆様からのご連絡をお待ちしております。
34 / 49«...1020...3233343536...40...»